《白い猫》 ピエール・ボナール

ボナールは白い猫がきゅーっと背中を丸めるしぐさをゆがみを使うことによってユーモラスな姿で創作されています。足をふんばって強く丸め、首をひっこめ、なんともいえない表情をしているこの不思議な動物は、飼いならされたようにも野性的にも見えます。
ボナールの習作から、画家は猫の姿や足の位置を決めるのに、長い時間を使ったことがわかりました。この作品のX線からもたくさんの変更があったことが分かり、その幾つかは目にも見えるほどです。ボナールは「アートは自然ではない」と語ったことがありました。ボナールの白い猫はまるでフランスのカリカチュア(風刺画)のようなっており、「観察と理解に長けた巨匠の中の天才による、コミカルでユーモアのある絵」(Elisabeth Foucart-Walter)と評されています。
この絵画の装飾的なスタイルは、曲がりくねった線が顕著で、背景の奥行がなく主題が平面的に置かれた作風は、1894以降のナビ派の典型といえます。日本画のインスピレーションが、非対称の構図や主題の選択にも色濃く表れています。ボナールは葛飾北斎(1760-1849)や歌川国芳(1797-1861)のファンでもあり、特に北斎や国芳が浮世絵に描いたお馴染みの猫たちにも影響を受けたようです。この作品のように、ボナールは猫にフューチャーした無数の作品を創作しました。時にはシンプルなディテールとして、大きく扱われることもあれば、小さく配されていることもあり、またこの《白い猫》のように、主題の中心として描かれることもありました。
《モスローズ》 ルノワール

モスローズというのは、つぼみに苔(Moss)のような腺毛がついたバラで、日本では「苔薔薇」と呼ばれたオールドローズの品種です。突然変異で誕生し、ビクトリア時代に流行したバラとしても知られています。花言葉は、「尊敬、愛の告白、無邪気、可憐、崇拝」など。
これは、50歳頃のルノワールが描いた作品でした。印象派から誕生した画家が印象派を乗り越え、探究し続けた独自の作風が確立していた頃でもありました。バラの形よりも、その自由なタッチで表現した幾重にも重なり合った花弁の印象を捉えた様子から、印象派時代の作風に近づけた作品といえます。
この作品は、当時医師で印象派の収集家でもあったジョルジュ・ヴィオ(1855-1939)が入手し、1907年まで手元に置いていました。その後、ルーヴル美術館絵画部門の学芸員として、モネ展やルノワール展などの回顧展を手掛けたポール・ジャモ(1863-1939)の手に渡り、最終的に国家に寄贈されました。
《黄色いコンソール》 ラウル・デュフィ

ラウル・デュフィは音楽家の一家に生まれました。父親は会計士として勤めの傍ら、教会の指揮者でオルガン奏者、母親もヴァイオリンを嗜むという音楽好き一家の中で育ち、感性を宿しました。
弟二人もプロの音楽家であり、そのうちのひとり、ガストンはフルート奏者で音楽批評家になったため、デュフィは多くの演奏会に招かれ、音楽家と交流する機会を得て数々の音楽シリーズの傑作を描きました。デュフィの作品にはどれも、優雅な音楽的要素が表れています。第二次世界大戦のさなか、デュフィは単色、あるいは鮮やかな色を限定した作品群を描き始めました。主題の多くは、画家のアトリエや自宅、そして音楽の世界です。
《黄色いコンソール》は、デュフィ晩年の作品ごとにある一色を基調としているスタイルで、この作品はイエローオーカー(赤みがかった黄色)の淡彩で描かれています。画面の三分の二を占めるこのルイ14世様式の重厚なコンソール・テーブルは、ペルピニャン(フランス南部、ラングドック=ルシヨン地方)にあるアラゴ広場に移った先のデュフィのアトリエに実在した家具でした。広場に面した大きな二つの窓の間に置かれていて、壁面には大きな鏡が取り付けてあり、デュフィはその鏡の装飾も譜面の後ろに描いています。ルネサンスの影響が残るバロックの豪華で重厚なテイストが伝わってくる直線と曲線が特徴のルイ14世様式のコンソールは、譜面から踊り出すような音譜、手前のヴァイオリンとともに絶妙なハーモニーを奏でています。
《夜会》 ジャン・ベロー
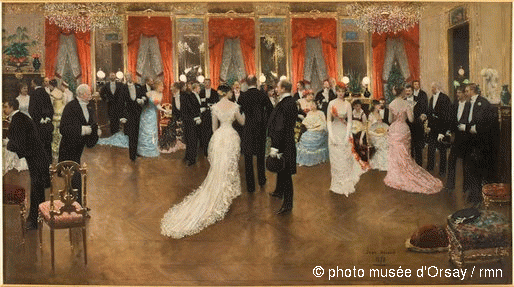
まばゆいランプ、重厚感のあるドレープで飾られたヴェルミヨン色のカーテン、その間には奥行の広がりを映す鏡、天井にはきらめくシャンデリア。豪華絢爛な広間でくり広げられる、パリが繁栄した華やかなベル・エポック時代の舞踏会の様子が精密に描かれています。
男性は正装の燕尾服に身を包み、女性はまるで夜会のフロワーに花を咲かせる長い引き裾ドレスの装いで、細やかなレースや刺繍はやわらかな質感まで伝わってくるようです。このような豊かなドレス、コルセットで絞められた細いウェスト、ペチコートで膨らんだヒップは、当時の女性ファッションの流行でした。
今では《夜会》で知られるこの作品は、《ホテル・カイユボット》という古いタイトルから、カイユボット邸で開かれた夜会だったという説もありましたが、オルセー美術館の公式サイトによると、これを示す書類は充分ではないとしています。カイユボットは裕福な画家で、ルノワールやモネなどの支援者として印象派の収集家でもあり、この時代を支えたことには間違えありません。
2016年夏に開催されたルノワール展では、ルノワール作《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》の他、オペラ座やテュイルリー宮での舞踏会をテーマにした同時代の絵画がひとつのコーナーを作り、その中でもひときわ鑑賞者の目を引いたのがこのジャン・ベローの《夜会》でした。
《大きな赤い室内》 アンリ・マティス

作品タイトルに「大きな」とつく通り大きめのキャンバスに、全体に広がる強烈な赤の色彩が飛び込む作品。一瞬奥行きが分からず平面と思いきや、2枚の絵画がかかる壁は、床と直角に交わり、空間構成をなしています。
アンリ・マティスは生涯にわたり、アトリエや旅先を含めて「室内」をテーマにした作品を描きました。「室内」というテーマは、マティス作品において一つのカテゴリーを築いています。長年さまざまな表現の変遷を経てマティスは「室内」を主題に制作を続け、本作品は晩年のマティスが室内を描いた最後の一点です。晩年、マティスは切り紙による作品が中心となりましたが、そうした表現方法を踏まえた上でのこの作品には、初期の室内を描いた作品よりも、切り絵さながらの即興的な遊びすら感じられます。
画面全体を赤が支配する中、画家はペアとなるオブジェの並置や対比を楽しんでいるようです。2点の絵画、2台のテーブル、2枚の動物の毛皮――カタチや色、モティーフが異なるオブジェが対で描かれますが、色やかたちは異なり、絶妙なバランスで保たれています。動物の毛皮にいたっては、まるで生きているかのようにユーモラスに描かれています。黒い輪郭線は強烈な赤い背景から浮き出るかのように表現されて、全体の絵画空間を構成しています。
マティスは豊かな色彩の中でも特に「赤」を多用した画家でした。しかしながら、マティスがこの作品を制作した時の写真が残っており、それによると、壁の色は当初「赤」ではないことが分かりました。途中で変えたのは、オブジェ固有の色彩を描くのではなく、画家が描く時の情感に響き合う色彩を選んだという見方もできます。「私は色彩を通じて感じます。だから私の絵はこれからも色彩によって組織されるでしょう」とは、「色彩の魔術師」ならではマティスの言葉です。
《アルジャントゥイユのレガッタ》 クロード・モネ
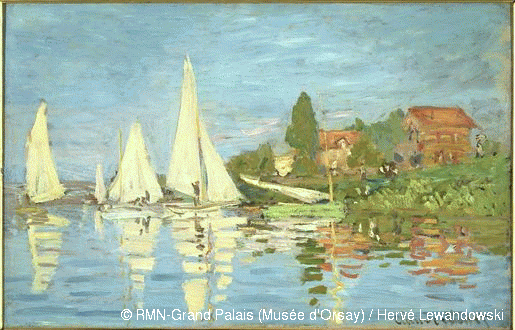
ボートは1830年頃からパリ郊外を中心とした地域圏、イル・ド・フランスで人気になりました。レース用のボートは、セーヌ河が拡張したため1850年からアルジャントゥイユで競うようになっていきました。パリと鉄道で繋がったことで一層アルジャントゥイユにはボート競技者が訪れ、日曜日には大勢の人が川付近に集まりレースを観戦していました。
クロード・モネは、アルジャントゥイユに1871年12月から1878年の半ばまで住み、その間に170点もの作品をこのセーヌ河畔で描きました。印象主義が芸術ムーブメントとして公やけに認められる2年前に、モネはこの風景を描いていたのでした。19世紀半ばにチューブ入りの絵の具が発明されたことにより、画家たちはアトリエを出て外で写生できるようになたため、この《アルジャントゥイユのレガッタ》も自然光の中で描かれたと推測されます。波打つ水面に景色が映って揺らめくさまに興味を示し、モネは空気と水の動きが光を変えゆく様子を捉えようとしました。このように揺れ動く水面に光が反射する状態を描く手法はこの作品以降モネの要素となっていき、《印象、日の出》においても中心的な特徴として用いられました。
この《アルジャントゥイユのレガッタ》は、1876年にギュスターヴ・カイユボットが入手し、1894年に国家に遺贈されました。1870年の初め、アルジャントゥイユにはモネだけでなく、マネ、ルノワール、シスレー、カイユボットがここで一緒に制作していたとされています。アルジャントゥイユ時代は印象主義の歴史で重要な一つの時代をなすもので、この作品はその代表的作品といえます。
《樹々の下の薔薇》 ギュスターヴ・クリムト

Roses under the Trees
この作品は、クリムトが1904年と1905年の夏のバカンス中に訪れていたアッタ―湖畔(オーストリア)のリッツルベルクと呼ばれる城のある島で描かれたものでした。クリムトの作品は230枚のうち50枚が風景画で、そのほとんどが頻繁に訪れたこのアッター湖畔で描かれたので、その風景画でもクリムトの特徴が顕著であるのがこの作品といえます。
キャンバスのほぼ一面が、均一な植物の密集で覆われ、まるでモザイクのような光景に仕上がっています。全体の中で変化となる唯一の要素は、薔薇の木と樹木の幹が形づくる平行線のモチーフだけです。画面の右側の上の端には地平線がわずかに見え、これが奥行きをもたらし、また鑑賞者の目の前に真っ平らに見える葉の群れと対比をなしています。
この作品には、装飾や文様を好んだクリムトの趣味がよく表れています。細かい点の筆触はタピスリーの紡ぎの色の重なりのようにも見え、正方形のキャンバスがいっそう惹き立てます。このような装飾は、クリムトの代表作品《接吻》の人物の下の部分にも登場します。クリムトは象徴主義的作品を独自の世界で生み出しウィーン分離派を創立しますが、一方この作品は、全体から穏やかな雰囲気が醸し出されています。依頼元による作品にはない、バカンス中に触れる自然への画家の優しいまなざしが感じ取れます。